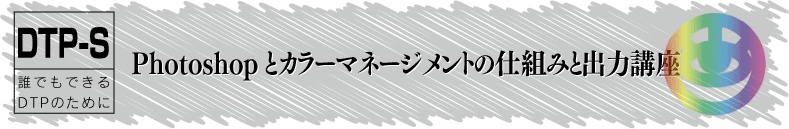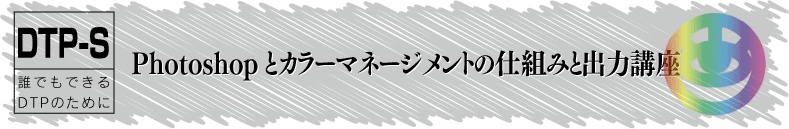|
|
|
|
「カラーマネージメントは難しい」と思っていませんか? 専門用語が飛び交い、成果もわかりにくいと思っていませんか。確かに「カラーマネージメントしなくても、DTPはできる」かもしれません。
とはいえ、カラーマネージメントは「常識」になりつつあります。カラーマネージメントがわからないと、CMYK変換もできないようになります。オフセットでも枚葉印刷するときと輪転機で印刷する場合では、CMYK変換のプロファイルも異なります。
ここでは、難解に見えるカラーマネージメントを、できるだけ「やさしく、わかりやすく」解説します。
|
■1-1 カラーマネージメントは色合わせを目的としない
カラーマネージメントが普及してきました。モニタもプリンタもカラーマネージメントに対応しています。印刷でも、カラーマネージメントして出力することも多くなってきています。カラーマネージメントデバイスの低価格化も普及を促進しています。
しかし、カラーマネージメントは一体なんのためにあるのでしょうか。何故、必要なのでしょうか。本当に必要なのでしょうか。また、それにコストや時間をかける価値はあるのでしょうか。それがわからないと、カラーマネージメントには取り組めません。
印刷物では、もともとカラーマネージメントは行われていませんでした。製版の時代は、色校正をチェックしそれに合わせて修正する作業で色を合わせていました。極めてに主観的な手法でのカラーマッチングです。その場その場の対応で、カラーマネージメントではありません。
製版時代の色校正は、カラーマッチングといっても、決まったルールがあるわけではありません。校正者の独断と偏見で可否が決まるのです。もっと極端にいえば、発注担当者がオーケーであれば、色は違っていてもかまわないのです。また逆に、オフセット印刷では再現できない微妙な差を、発注担当者が要求すれば、それが印刷基準になったのです。
「色の基準を作ろう」というのが、カラーマネージメントの始まりといってもいいでしょう。もっといえば、基準ができれば、色校正はやりやすくなるということでしょうか。
一般に「カラーマッチングとカラーマネージメントは違う」といわれます。もちろん、この2つは同じものではありません。この文脈で使われる「カラーマッチング」は、ルールのない色合わせのことを指しています。さらに、「結果さえよければOKというやり方は駄目だ」というニュアンスを含んでいることが多いようです。
しかし、カラーマネージメントの目的は、カラーマッチングです。色を合わせることです。ただし、色を合わせるための仕組み(システム)や方法(メソッド)を統一しましょう、ということなのです。
仕組みや方法を統一するということは、逆にいうと、仕組みや方法を優先するということです。それらを優先すれば、カラーマッチングの部分は優先されないことになります。色を合わせるより、共通の仕組みでカラーを管理するものがカラーマネージメントなのです。
「カラーマネージメントしても、色は合わない」と言われますが、合わないのではなくて、色を合わせることが最優先になっていないのです。変換したときの色の「ブレ」をある程度の幅に収めることが、カラーマネージメントなのです。
カラーマッチングのみを優先していくと、「そのときだけ色が合えばいい」ということになります。同じカラー原稿を利用して、別の印刷物に使うとき、仕組みや方法が統一されていないと、色が合っているように見えても、同じ色にはなりません。
また、次に同じカラー原稿を利用しても、同じ色を再現することできなくなります。色を合わせる仕組みができていれば、一度、カラーの変換や再現の方法が確立されれば、次は色校正しなくてもかまわないのです。
本来のカラーマネージメントは、カラーマッチングを果たしつつ、カラー変換の仕組みや方法を統一するべきものです。最終の目的は、どのような場合でも利用できて、なおかつ再現性があり、色も合うべきものです。
ところが、現在のカラーマネージメントは、やっと仕組みができあがったところで、本当の目的であるカラーマッチングが、なおざりにされているきらいがあります。つまり仕組みを確立することが最優先されていて、色を合わせることは後回しになっているのです。
現実には色を合わせるのは難しいのです。なんといっても、色は主観で左右されるからです。校正する人の主観だけでなく、そのときの感情によっても色の感じ方は異なります。感情が高ぶっているときは、ビビットな赤は、さらに赤く見えるのではないでしょうか。アルコールが入っていれば、色を的確に判断することはまずできません。
さらに、どう転んでもカラーマッチングが不可能なこともあります。RGBからCMYKに変換するときは、実質的にはカラーマッチングはできません。RGBとCMYKは、水と油みたいなものですから、色が合うわけないのです。RGB同士とか、CMYK同士であれば、かなり精度の高い変換がカラーマネージメントでできますが、RGBからCMYKへの変換では、まず無理です。より近い色に変換するしかありません。
カラーマネージメントは、仕組みを提供するだけです。ですから、色は合うかどうかは別の問題です。どのくらい色が合うのかということは、カラーマネージメントシステムの「精度」なのです。カラーマネージメントでは、仕組みを提供するだけです。その仕組みが、まだまだ、発展途上なのが現実なのです。
|
|
DTP-Sウィークリーマガジン/218号/2005.7.1配信
|
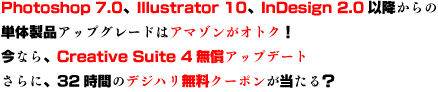
|
|